|
「言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか」(今井むつみ、秋田喜美:著、中公新書)は、言語の起源と進化、子どもの言語習得、言語の本質とは何か、についての論考である。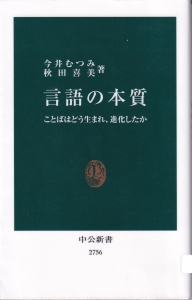
本書の中核をなすのは、人間特有の能力である「アブダクション推論」が、言語の起源と発達に大きく寄与している、という仮説であろう。言語の習得について本書では、「言語習得とは、推論によって知識を増やしながら、同時に”学習の仕方”自体も学習し、洗練されていく、自律的に成長し続けるプロセスである」としている。
また、これに関連して「ブートストラッピング・サイクル」というモデルが提唱されている。このモデルは、「最初の端緒となる知識が接地されていれば、その知識を雪だるま式に増やしていくことができる」というものである。
本書の概要と感想を述べる前に、「言語の起源と進化」に対する著者の立場を明らかにする必要があるだろう。なぜなら、言語の起源と進化に関しては、(他の書籍を読んで)大きく2つの立場があると感じているからである。
ひとつの立場は、言語の獲得はヒトの進化の過程における突然変異的なものであり、言語を習得するうえで生得的な(遺伝によって継承される)部分がある、という説である。
今一つの立場は、言語の獲得に突然変異は関係なく、言語はヒトが長い時間をかけて習得したものであり、生得的な部分は存在しない、とする立場である。
このように真っ向から対立する立場があること自体、「言語の起源と進化」が根の深い問題を抱えた、未解決な課題である証しなのだろう。
本書を読んだ限りでは、著者の立場は後者であると思われる。
ただ、本書のなかで「子どもの言語習得」に関しては気になる点があるので以下に記しておく。
子どもが母語を習得することを、習得ではなく「母語の獲得」と言って区別する本もあるという点だ。
子どもは母語を非常に短期間で習得(獲得)できることから、何か生得的な(遺伝情報によって継承される)部分がある、とする説にも一定の説得力があると感じる。
実際、子どもが母語を獲得できる時期は限られており(臨界期)、私たちが外国語を習得するときの苦労を考えると、こどもは非常に短期間で母語を習得していると感じる。
本書は言語の起源と発達に、ヒトが有するアブダクション推論の能力が大きく関係している、という点がユニークであるが、「オノマトペ」の話から始まっている点も非常にユニークだと感じた。
最初は、「なんでオノマトペ?」と思ったが、読み進めるうちに著者の意図が分かってくる。(オノマトペはフランス語で「名前を作る」という意味があるそうだ)
オノマトペの特徴はアイコン性(形式と意味に類似性がある)である。形式と意味が似ているから、乳幼児と母親との会話にはオノマトペが多い。また、言語の起源と進化を考えると、形式と意味が似ている方が習得が容易で簡単なコミュニケーションは可能に思える。
本書には、「アイコン性の輪」という仮説も紹介されている。
子どもの言語獲得に関して、本書には面白い話が出ている。
「多くの2歳、3歳児は色に関して「アカ」や「キイロ」と発語できるが、様々な積み木の中から「アカい積み木を取って」と指示されても正しく積み木を取ることができない」
そうだ。これは、言葉と(それが指し示す)モノとの繋がりが一方向であるためらしい。それが子どもの成長に伴って、言葉とモノとの繋がりが双方向になるのだろう。
本書には「対称性推論」という能力についても説明がある。これは発生した事象を見て、その原因を推論する能力のようだ。
例えば、道路が濡れているという事象を見て、これは雨が降ったからに違いない、と原因を推定する能力である。この対称性推論の能力は、ヒトが言語を持つようになった要因の一つと考えられている。
なお一般の動物は(ごく一部の例外を除いて)対称性推論が出来ないそうだ。
本書には、最近話題になることが多いLLM(大規模言語モデル)にも関連する課題、「記号接地問題」への言及がある。
この課題は、認知科学者のスティーブン・ハルナットのAI(人工知能)に対する批判から始まったようだ。
「記号の意味を記号のみによって記述しつくすことは不可能である。基本的な一群のことばの意味はどこかで感覚と接地していなければならない」
という指摘だ。
基本的な一群のことばは「ヒトが身体を経て得られる感覚や、知覚、感情などに繋がっている必要がある」ということである。
本書にある「ブートストラッピング・サイクル」モデルでも、「最初の端緒となる知識が接地されていれば、・・・・」と書かれている。
一方で、現在のLLM(大規模言語モデル)には「接地していることば」はないように見える。本書にもこの点に関する言及はあるが、かなりあっさりした記述になっている。
他の書籍によれば現在のLLMは、「自然言語処理に必要な文法や知識、感情、推論などを、単語を予測するタスクを通じて学習する」と考えられている。
単語を予測するタスクとは、コーパスと呼ばれる大量のテキストをLLMに読み込ませて、文脈から単語を予測する事前学習のことである。
現在のLLMは大量のテキストを学習することで、単語の意味に相当するものを文脈から学習しているようにも見える。果たして、LLMは単語の意味や文の意味を知っていると言えるのだろうか?
もし一部の単語でも、その意味に相当するもの(概念)を獲得していれば、LLMは「接地していることば」を持たないのに言語(の一部)を習得したのだろうか?
もしそうなら、LLMの学習形態は人間のそれとは異なるという点で、かなり画期的なことだと思う。
しかし、一般的には(他の書籍などによると)現在のLLMは単語の意味を理解できない、と考えられている。いや、そもそも単語や文章の「意味を理解する」とはどのような事態なのかが明確でないのかもしれない。
専門外の私にはこれ以上のことは分からない。「意味を理解するとは何か」という問いも、このブログで何度か取り上げたが(今のところ)明解な仮説には出会っていない。
本書は言語を考えるうえで示唆に富むところが多いが、私が今一つ気になっていることがある。それは言語と思考との関わりである。
本書の主軸は、コミュニケーションの媒体としての言語であるが、思考の手段としての言語もあるのではないか、という点である。私たちは物事を考えるときに言語(母語)を使って考えているように思える。この点も専門外の私にはよく分からないことが多いが、興味を駆り立てるテーマである。
|
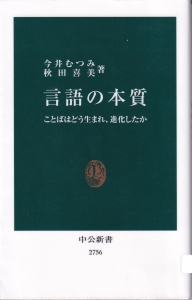

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません