エッセンシャルワーカーとIT業界
「エッセンシャルワーカー」(田中洋子:編、旬報社)は、そのサブタイトル「社会に不可欠な仕事なのに、なぜ安く使われるのか」にあるとおり、エッセンシャルワーカーの労働条件の過酷さや、低賃金の実態をあぶり出している。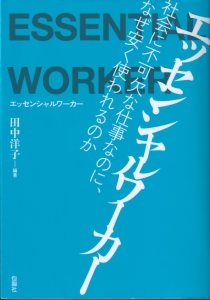 本書の目的は、 ①現場を担う人々の働き方を、現場に即した形で明らかにすること(現状分析)。 ②いつからどのようにしてエッセンシャルワーカーの働きが悪化したのかを分析すること。 ③どうしたら現在の状況を改善できるのかを、ドイツの例を参考に考察すること。 である。 ①の「現場に即した形」にあるとおり、本書にはスーパーマーケット、外食チェーン、自治体の相談員、保育園、学校の教員、ごみ収集作業員、看護師、訪問介護職、運送業、建設業、アニメーター、それぞれの具体的な事例が紹介されている。 本書ではエッセンシャルワーカーを、以下の主要な5類型に分類している。 ①小売業における主婦パート(主婦を中心とした低処遇のパートタイム) ②飲食業における学生バイト ③公共サービスの担い手の非正規化・民営化 ④女性中心の看護・介護職 ⑤委託・請負・フリーランスの担い手 本書で紹介されているエッセンシャルワーカーの働き方や組織構造には、多層下請け構造やフリーランスの存在など、私たちIT業界にも共通するところがある。これについては、後ほど考察する。 本書には、思っていた通りというか、「ブルシットジョブ くそどうでもいい仕事の理論」からの引用がある。 本書では、エッセンシャルワーカーの処遇(労働条件、賃金)が悪化した原因は、(業種別にみればそれぞれ個別の理由があるけれども)、大まかにつかむと以下のようなことが考えられる、としている。 ・1990年代以降の長期不況と自由化政策のもとで、日本的雇用システム(終身雇用や年功序列型の賃金制度)を維持することが困難になり、コスト削減や人件費削減が進んだ。 上記のコスト削減、人件費削減に用いられた手法が、労働者の非正規化であり、多重の下請け構造であろう。 この点、ドイツの事例は賃金制度や労働条件が分かりやすく、公平性が高い。 人材不足で特に危機的な状況にあるのが訪問介護職である。 コスト削減、人件費削減が進んだのは民間だけではない。 |
|
|
| 以上、本書の内容を概観したが、IT業界にも同じような構造があるので、この点を考えてみたい。私は常々IT業界と建設業界には似たところがあるなあ、と思っていた。 一つは多層下請け構造であり、この構造のもとで職種も上流工程と下流工程に分かれている。 IT業界(ここではエンタープライズ系を指す)では、元請けのSIヤーが提案活動や設計の上流工程、PJ管理を担うケースが大半である。 そして、プログラミングやテスト工程は下請けや、下請けに参入したフリーランスが請け負うことが多い。 下請けの構造は多層化している場合がある。 建設業も、顧客への提案や上流の設計を元請けが実施して、建築現場を下請け企業や一人親方が担っているようだ。 2010年時点で、世の中のフリーランスの大半(49%)は建設業に従事しているそうだ。多層下請け構造の問題点の一つは中間搾取である(言葉が悪いが)。 元請けから下請けに流れるお金は、多階層の層が多いほど、中間でとられる管理費(と称するマージン)が増えて、現場の労働者が得る収入は低くならざるを得ない。 現場の労働者が低賃金になると、入職者が減少して労働力不足、人材不足を招く。 このような多層下請け構造は運送業にもみられる。トラックドライバーの賃金水準低下と、人材不足はいま、「物流の2024年問題」として騒がれている。 IT業界で多層下請け構造が出来た理由は、人材の流動性を高めて要員調整を柔軟にするためだと考えられる(もちろん、価格交渉を行うことでより安い下請けを使いたいという動機もあるだろう)。 IT業界は世の中では進んだ業界だとみられるかもしれないが、現実には「労働集約的」な産業である。 IT業界も、今後AI(大規模言語モデルなど)の導入でプログラミングの自動化や、設計の自動化が進むかもしれない。 いまひとつIT業界と建設業界で共通するのが「偽装請負の問題」である。 |
|
|
| 補足:プロジェクトの要員規模 みずほ銀行のMINORI(勘定系システムを刷新、統合するプロジェクト)は、ピーク時8,000人のエンジニアが参画(推定値)と言われており、文字通り日本で最大規模のシステム構築プロジェクトであった。これを見ても明らかなようにIT業界(エンタープライズ系)は労働集約型の産業だといえる。 |
|
|
| 2024年1月11日 追記: 書籍「エッセンシャルワーカー」(田中洋子:編、旬報社)にも関連する記事が、朝日新聞に掲載されていた(2024年1月から始まった不定期の連載?)。記事のタイトルは「8がけ社会」。 「8がけ社会」とは、現役世代の数が今の8割(8がけ)になる2040年のことである。今の8割の人手で社会をまわし続ける方法はあるのか? という問いである。 労働力不足の影響を最も受ける職種はエッセンシャルワークであろう。連載記事では、トラックドライバーや介護士、建設業の派遣労働者など、エッセンシャルワーカーの実態が描かれるとともに、掲題の書籍ではあまり触れられていなかった視点が提示されていた。 ・女性の低待遇はなぜ生まれ、なぜ防げなかったのか。 バブル崩壊後も日本型雇用(年功序列や終身雇用)を維持しようとした結果、女性は補助業務に押し込められ、さらに非正規化が進んだ。女性の待遇を男性と対等にしようとする試みは「おじさんの壁」に阻まれた。 非正規雇用がもたらすマイナス面を最も被ったのがロストジェネレーション(ロスジェネ)世代である。 ・東京一極集中による地方の衰退 ・労働力不足の対策として、ロボットの導入や外国人を雇用する試みが進んでいる。 |

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません