高校の「情報Ⅰ」を読む
高校の「情報Ⅰ」は、2022年度から新学習指導要領で必須化された科目のようだ。どのような範囲とレベル感なのか、気になったので教科書を読んでみた。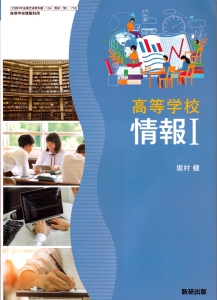 なお、2023年に選択科目として新設された「情報Ⅱ」というのもあるようだ。 最初にお断りしておかなければならないことがある。それは、私自身の経験に関することである。 私は長くIT業界で仕事をしてきたが、それはエンタープライズ系という、限られた範囲でのことである。 IT業界には、これ以外に組み込み系や、インターネット系(この呼び名が正しいのか、いささか不詳)の仕事がある。エンタープライズ系とは、主に企業の基幹業務を扱う領域である。従って、ここに記す教科書への感想や指摘は、私個人の意見であり、私が経験してきた領域を基礎にしているから、偏っている可能性がある。 IT業界で仕事をしてきて気になっていたのは、カタカナの用語やアルファベットの略称が多いことである。そしてそれらの用語や略称が正式な言葉なのか、ジャーゴン(流行り言葉)なのかが分からない、ということだ。 これは私だけでなく、IT業界で仕事をしてこられた方なら同意いただけると思う。もちろん、ネットで調べればそれらの用語の出典は分かると思うが、ほとんどの人が無意識に使っている(と思う)。 そして、これらの用語のなかには時間の経過とともに忘れ去られたものが多くある。変化(進化)が激しい業界だから、新しい用語が出てきたり、古い用語が廃れていくのは当然の流れではあるのだが。 ここで問題になるのは、「高校Ⅰ」の教科書に登場する用語とその定義だと思う。 幾つかの用語を拾ってみる。教科書では、IT(情報技術)と記されていて、「ほぼ同じ意味で情報通信技術(ICT)もよく使われている」とある。ITという用語が定着しているなかで、なぜICTという言葉が登場したのだろう?(私の記憶ではICTという用語はITという用語よりもずっと後から登場した) ICTは、Communication(通信、伝達)を強調したのだろうけど、今日ほとんどのコンピュータはネットワーク(インターネットを含む)に接続している。あえてComunicatiinを強調する必要はないと思う。 無駄に新しい用語を増やす必要はなかったのではないか。教科書には、情報技術という用語のほかに「情報システム」という言葉が登場する。 情報システムとは、「通信回線を用いてコンピュータを相互に接続し、情報を収集・処理・蓄積・伝達して活用するシステム」と定義されている。個人的には、「情報システム」よりも「情報処理システム」という言葉の方が馴染んでいる。さらに、(文脈によっては)ITを情報処理システムという意味で使う場合もあると思う。 DX(デジタルトランスメーション)という用語も同じだ。この言葉はここ2~3年でよく目にするようになった。技術の進化が早いから、最近の用語や技術も教科書に取り入れざるを得ないのは分かる。しかし、この言葉も定義があいまいなまま使われている。 教科書では「ものごとのやり方自体を大きく変えて、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」と定義している。インターネットを検索してみると、「デジタル技術を活用して、新しいビジネスの仕組みを構築して競争力を高めること」といったニュアンスの説明もある。これは経済産業省の定義に近い。 個人的には、この言葉は一種のジャーゴンであり、デジタル技術を活用してBPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)を実行する、というニュアンスだと思う。BPRという用語があるのに、なぜ新たにDXという言葉を作り出したのか?さらに、DXに関する記事(コンピュータ関連の雑誌の記事)を読むと、BPRとは思えないものまで事例として取り上げられていたりする。 すなわち、IT業界の用語には、定義が結構いい加減なまま使われているものが多い(と思う)。IT業界の人たちは(私を含めて)用語の定義を深く考えないで使っているのが実情だろう。言葉は悪いがフィーリングで使ったり、前後の文脈から判断して意味を汲み取っているようなとことがある。 なぜ、用語に拘るかということだが、教科書に記載するとなれば用語の定義は厳密である必要があると思うからである。ジャーゴンまで取り上げると、定義は不正確になる場合があるだろうし、時間がたつと廃れてしまうこともある。最新の動向も含めたいという著者の意向は分かるが、なんとも悩ましい。 個人的には、この言葉はもはや過去のものではないか、という用語もある。 そのひとつが「ユビキタスコンピューティング」である。これと似た概念に「IoT」がある。IoTは最近よく目にするが、ユビキタスという用語は最近見かけない。 DX、ユビキタス、IoTに共通するのは、これらの言葉がコンセプト(または考え方)に近いということだ。同じようなコンセプトの用語が、時代の変化に応じて新しい用語に置き換わる(あるいは意図的に置き換える)、というのはこの業界ではよくある現象だ。クライアント・サーバやオープンシステム(オンプレミスに対する用語)などの言葉も最近は見かけなくなった。私が読んだ教科書の著者は坂村健氏である。坂村氏はTRONの開発をけん引した方である。当然この教科書にもTRONのことが(少しばかりだが)記載されている。 私の記憶ではTRONは一時期話題になったが、最近はほとんど目にすることがなくなったので、廃れた技術なのかと思っていた。しかし、組み込み系の分野ではTRONは事実上の業界標準(デファクトスタンダード)だそうだ。(これなども、私の知識が偏っている証左だ) さて、用語に関連してこの業界での”あるある”が「ー(長音)」の扱いだ。「コンピュータ」と書くが「コンピューター」とは書かない。教科書もそうなっている。英語の発音だと後者に近い気がするが、なぜか「コンピュータ」と書く。 エンタープライズ系(企業の基幹業務系システム。銀行の勘定系システムを含む)では、データベースとオンライントランザクション処理が重要な技術のひとつである。教科書では、「データベースソフトウェア」という言葉と「DBMS(データベース管理システム)」という言葉を区別しているようだ。教科書だからベンダーの固有名詞は載せられないのだろうが、例えばOracleはどっちなのか? DBMSに関しても、RDBについてはほとんど触れていないのに、最近の「キー・バリュー形式」は記載がある。RDB(リレーショナルデータベース)は、汎用機からオープンシステムへと時代が変化する中で重要な位置を占めていたから、もう少し踏み込んだ説明があってもよいと思う。汎用機(メインフレーム)が主流の時代は、データベースは階層型が主流であった(と記憶している)。 教科書にはトランザクション管理の説明や、ロック(テーブルロックや行ロックのロック)や排他制御の説明があるが、OLTPという用語は登場しない。 最後に情報システムの分類(カテゴリー)について記しておきたい。教科書にはいくつかの情報システムの名前が登場するが、それらをどのように分類するかの記述がない。個人的には何らかの「軸」でシステムを分類した方が、システムの目的や用途が分かりやすい。また、歴史的な流れも見通しが良くなると思う。 |

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません