福永武彦「死の島」
著者の福永武彦は昭和49年、「死の島」の序文で次のように書いている。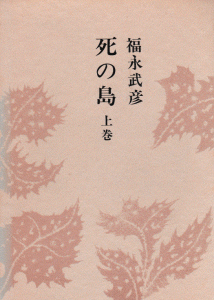 「この小説が私のこれまでの作品の倍以上の長さがあるからと言って、作者の抱負もまた倍ほど大きいと言ったものではない。」 「またこれを書き上げるのに長い時間を要したからという理由で、特別扱いをされるのも心外である。」 「「死の島」は私の書いたものの中では最も読まれていない作品ではないかと思う。」 この本「死の島」、私が読んだのは、昭和49年新潮社発行の「福永武彦全小説」の第10巻、第11巻に収められたものである。 この小説はその後同じ新潮社から文庫本が刊行されたが、やがて廃刊になったと記憶している。現在は、講談社文芸文庫で入手出来るようだ。 死の島というタイトルは、スイスの画家アルノルト・ベックリンの絵画に由来する。 この画は、墓地のある海上の小さな孤島をめざし、白い棺を乗せた小舟が暗い海原を漕ぎ進む様子を描いた作品である。 ベックリンは、このモチーフに随分と執着していたようで、生涯にこの題材で5点の作品を残したという。 但し、小説の中では、直接このベックリンの絵画が登場するわけではない。登場人物の一人、萌木素子が描いた画がベックリンの死の島に似ていることに由来する訳だが、物語のストーリーもこの絶望を象徴する死の島に向かって流れていくことになる。 この小説の主な登場人物は、相馬鼎と相見綾子、そして画家の萌木素子である。 萌木素子は、広島で原爆の被害に遭い、それ以降は他人の愛を全く寄せ付けない、絶望と孤独の中を生きる女性として描かれている。 相見綾子は父親が医者の家庭に生まれた、育ちの良いお嬢様のようであるが、母親の愛情にはあまり恵まれない境遇であった。 相馬鼎は、小説家を目指している、出版社に勤める編集担当で、相見綾子と萌木素子の両方を愛しているという、随分とご都合主義の、あるいは、どちらの女性を本当に愛しているのか自分でも分からない、少々優柔不断な男である。 ある日、相馬鼎は電報を受け取る。電報の内容は、相見綾子と萌木素子が旅先の広島で服毒自殺を図ったという、相馬鼎にとっては思いもよらぬ、衝撃的なものであった。 さらに、そのうちの一人は既に息を引き取ったと書かれているのだが、それが相見綾子なのか萌木素子なのかは分からない。 相馬鼎は東京から汽車に乗り、広島の病院へと急ぐ。 物語は、相馬鼎が電報を受け取った、その当日の目覚めから、病院へ到着し病室を訪れるまでを描きつつ、その合間、合間に複数の物語の断章が挿入されるという手法で展開されていく。 挿入される複数の物語の一つは、相馬鼎が相見綾子と萌木素子という、2人の女性と出会ってから今日までの経緯を綴ったもの。 今一つは相馬鼎が創作中の小説、その小説も実はこの2人の女性を題材にしたものであり、現実を投影したようなストーリーになっている。 今一つの物語は、2人の女性と関係がある”ある男”の物語。 そして、今一つは萌木素子の内面、ないしは内面に棲む”それ”を描いた物語である。 複数の物語は広島の病院、死の島の墓地を予感させるその場所に向かって収れんしていく。 作者は、この作品について「現代における愛の可能性、或いは不可能性という主題を、原爆の被害者である一人の女性をめぐる数人の人物との関係に於いて捉え、そこに死の島である日本の精神状況を内面的に描き出したい・・・」と綴っている。 |
