高校の「情報Ⅰ」を読む
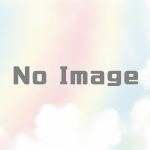
高校の「情報Ⅰ」は、2022年度から新学習指導要領で必須化された科目のようだ。どのような範囲とレベル感なのか、気になったので教科書を読んでみた。
なお、2023年に選択科目として新設された「情報Ⅱ」というのもあるようだ。
最 ...
なお、2023年に選択科目として新設された「情報Ⅱ」というのもあるようだ。
最 ...
新型コロナ対策の不都合な真実?
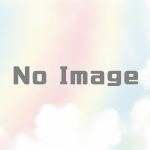
(1)借金(国債)頼みの新型コロナ対策新型コロナウィルス(COVID-19)の感染が拡大し、2020年4月、全ての都道府県を対象に緊急事態宣言が発令されるに至った。
旅行業や飲食業、百貨店、旅館、スポーツジム、 ...
2025年問題(2025年の崖より深刻なもの)
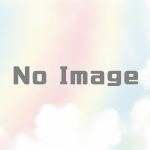
IT業界では昨今「2025年の崖」という言葉(警告)が声高に叫ばれている。これは、経済産業省の「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」が発端のようである。
「2025年の崖」とは、複雑化・老朽化・ ...
「2025年の崖」とは、複雑化・老朽化・ ...