山本周五郎「青べか物語」
| 青べか物語は千葉県浦安市(作品の中では浦粕町という呼び名である)を舞台にした連作小説である。 この作品が発表された昭和35年ごろ、この作品が小説か否かという論争があったらしい。作者によればこの作品は小説ではなく、小説のエッセンスだけを抽出した作品ということのようだ。 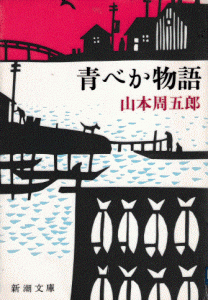 青べかの「べか」とはべか船のこと。べか船とは櫂でこぐ(時に小さな帆を掛ける)一人乗りの小船である。この本、表題こそ青べか物語となっているが、内容は東京から浦粕町にやってきた私が見た、浦粕町の風景や、そこで働く人々、あるいは子供たちの日常の出来事を写生した小品集である。 作品に登場する私とは、作者の山本周五郎自身のことであるが、作品に描かれている内容が実際に作者が見たり経験した事実なのか否かは定かではない。 例えば、作品の中では私は浦粕町に3年余り住んでいたことになっているが、実際のところは1年弱だったようだ。この辺りの事情は「青べか慕情(写真:石井久雄、文:木村久邇典)」に詳しい。 作品に描かれている浦粕町は、昭和3年~4年頃の浦安である。 地下鉄東西線が開通するまでの浦安は、東京の近郊ながら陸の孤島と呼ばれ、貝と海苔と釣り場で知られた漁村であった。 東京と浦安を結ぶ主な交通手段は船であった。深川の高橋と江戸川に臨んだ千葉県行徳町を運航していた定期の蒸気船である。 「高橋から船で東京湾に出て、江戸川に入って浦安に行くか、陸路を通るとすれば錦糸町から城東電車で今井に行き、江戸川は渡しに乗って浦安に上がる」(「青べか慕情」より) 浦安の風土を代表する象徴的な風景が「沖の百万坪」である。作品の中では次のように表現されている。 「そこはたしかにその名にふさわしい広さをもっていた。畑といくらかの田もあるが、大部分は葦や雑草の繁った荒地と、沼や池や湿地などで占められ、その間を根戸川(旧江戸川のことだろう)から引いた用水掘が、荒地に縦横の水路を通じていた。」 さらに沼や池や葦の繁みには、カワウソやイタチなどが棲んでいたという。  「青べか慕情」の写真でみると、沖の百万坪は1970年くらいまでは未だ残っていたようで、その後埋め立てられて団地や住宅が次々と建設されていった。 「青べか慕情」の写真でみると、沖の百万坪は1970年くらいまでは未だ残っていたようで、その後埋め立てられて団地や住宅が次々と建設されていった。
作品に登場する風景は、のどかで、どこか懐かしい漁村の風景だが、そこに登場する人々は、いたずら盛りの悪がきや、よそ者からぼったくろうとする者、両親に捨てられて乞食同然の暮らしを強いられている幼い姉妹、信じ難いほど劣悪な環境で働く石灰工場の人々などなど・・・・、悲惨で、猥雑でありながら活気に溢れ、そしてどこか滑稽だったりする。そして全編を通じて物語の背後に作者の穏やかな眼差しが感じられる。 ”繁あね”は悲惨で過酷な運命を背負いながらもたくましく生きている。 |

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません