渡辺正峰「脳の意識 機械の意識」は、そのタイトルからAI(人工知能)と意識(または心)に関する論説かと思ったが少々違った。
サブタイトルに「脳神経科学の挑戦」とあるように、脳神経科学からみた「意識の解明」への取り組み状況を解説した書籍である。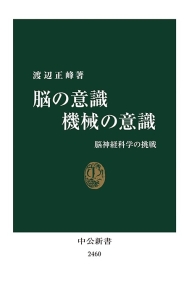
とはいえ、本書には深層学習に関する解説もあるし、何といっても「機械は意識を持つことが出来るのか」、という壮大な(そして少々奇想天外な)テーマが本書の一つの柱になっている。
「意識の解明」にある根源的な問題意識は、
「(脳の仕組み、すなわち)ニューロンの発火という比較的単純な仕組みから、いかにして意識が形成されるのか」
という点にある。
この問題認識からわかるように、著者は「意識は脳に宿る」という前提に立っている。この前提を読者が受け入れるか否かで、本書に対する関心の度合いや、論説に賛同できるか否かといった態度が変わってくるだろう。
以前にも書いたが、「心と脳 認知科学入門」(安西祐一郎 岩波新書)のなかに以下の指摘がある。
「心の研究を重視する人は、脳の研究をしたところで心は分からないと考えていることが多い。一方、脳の研究を重視する人は脳を研究すれば心が分かると思っている人が多い。」
脳科学者である著者は後者であるが、私は門外漢ではあるものの前者の意見に近い。従って、本書の論説に対しては納得感を得られない部分が多々ある。
意識が宿る場所として著者が考えているのは「神経アルゴリズム」と呼ばれるものだ。
「筆者が意識の自然則の対象として提案しているのは、情報としてのニューロンの発火そのものではなく、その情報を処理し、解釈する神経アルゴリズムである」
「意識の自然則における客観側の対象の第一候補として考えるのは、生成モデルと呼ばれる神経アルゴリズムである」
神経アルゴリズムがいかなるものなのか、詳細は良く分からないが、コンピュータプログラムのアルゴリズムのようなものだと思われる。(このテーマを追求していくと、ロジャー・ペンローズの「意識と計算可能性」の問題に突き当たりそうだが、本書ではこの点に関して特に言及はない。ペンローズは現在のチューリングマシンは、仕組み的に心を持てないと主張した。最初に、「脳機能すべてをアルゴリズムに還元することは不可能だ」と主張したのは、不完全性定理で名高いクルト・ゲーデルである。)
著者が意識が宿る場所として、神経ニューロンではなく、神経アルゴリズムを仮定している理由は、以下である。
「ニューロン単体としての働きはたかが知れている。他のニューロンからの電気スパイクを重み付けしながら足し合わせ、それが閾値に達したときにに自らも電気スパイクを出力する。・・(中略)・・ニューロン単体に意識の源となるような未知の仕掛けが存在する可能性は極めて低い」
脳をニューロンのレベルまで細かく分析していったが、結果、そこには意識を宿す仕組みは見つからなかったと言っている。
これは、「部分の総和は全体にならない」と言っているのに等しいのではないだろうか。すなわち、意識や心は科学的アプローチ(分析的手法や還元主義)では解明できない可能性を示唆している(ように思う)。
著者も指摘しているように、意識の問題を扱う際の障壁は、「科学的手法」すなわち「主観と客観」の問題である。
「脳の客観を完全に解き明かしたとしても、脳の主観(意識のこと)には一歩も近づかない。最大の問題は、我々が客観と主観とを結びつける科学的原理を一切持たないことだ」
「従来科学の枠内では意識を解き明かすことはできない。それは従来科学が客観の中で閉じているからだ。・・・・意識の科学は既存の科学から逸脱する」
それでも著者は科学的アプローチによって意識に迫ろうとしている。(本書には登場しないが、科学的アプローチ(還元主義)を批判して独自の理論を展開しているのがマイケル・ポランニーである)
著者は意識には「意識の自然則」があるとする。(このような立場をとる人は他にもいる)
そして意識の自然則が自然則であるための条件として、「検証可能性」をあげている。しかし、少し考えてみれば明らかなように、この「検証可能性」も客観のなかに閉じていると思われるのだが・・・。このあたりの論理は私には良く分からなかった。
著者が意識を問うそもそもの出発点は、
「デカルトの、我思うゆえに我あり、の我こそが本書の対象である意識である。意識を問ううえでの出発点であり、ただ一つ、存在のゆるぎないもの」である。
上記の我は「自我」と考えられる。人間の誕生から成長の過程を考えると、自我が最初からあったとは考え辛い。(意識は自我が生まれる前からあるのだろうが・・・・。西村尚子「三歳までに脳で何が起きているのか?」によると、自我や意識が乳幼児期のいつ頃、脳のどこで芽生えるのかといったことは、ほとんどわかっていないそうである。)
人間の成長過程で、自我は外界(客体)との関係において成立する(芽生える)と思われる。
さらに、人間は自我を脱落することも可能である。道元禅師の有名な言葉に心身脱落があるし、これと類似した言葉に父母未生以前というのもある。これらは、自我と客体から生じる差別を超越した事態だと思われるが、詳しいことは私にはわからない。
いずれにせよ、自我が脱落しても意識は存在していると思われる。そして、残念ながら科学とは、自我と客体が存在すること(二項対立)が前提であるから、科学的手法で意識に迫るのは困難だ。
意識や心を考えるとき、「環境(他者を含む外界との関係)」は極めて重要な要素だと考えられる。本書の論理にはこの点が欠落していると感じる。
例えば、「ここでいう心とは、人と人の相互作用のなかで現れいずるものである」(「心を発見する心の発達」板倉昭二 京都大学学術出版会)のように、心理学では心と環境との関係を重要視している。(アフォーダンス理論や生態学的心理学などでも同じようだ)
もしも「意識の自然則」があるとすれば、それは環境(自己の外部)を含む法則ではないかと思われる。
従って、本書が主張しているNCC(固有の感覚意識体験(クオリア)を生じさせるのに十分な、最小限の神経活動と神経メカニズム)が発見されるか否かに関して、私自身は今のところ否定的感想を持たざるを得ない。
本書ではじめて知ったことだが、国際的に認められた日本人初の脳科学者は、井上達二氏(眼科医)だそうである。井上氏は、日露戦争で 目に戦傷を負った軍人を治療するなかで、視野欠損の位置と脳の損傷個所との間に対応関係があることを発見したそうである。
このようなところにも、科学の進歩と戦争との関係性がみられることに少なからず驚いた。
|
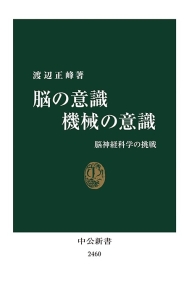

ディスカッション
コメント一覧
私見ですが、最初は単なるでたらめなアルゴリズムが、外部刺激によって淘汰され、残ったアルゴリズムがシナプス結合の強弱つまり記憶となり、記憶の連続性が意識となる。